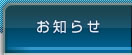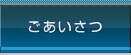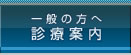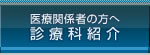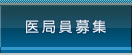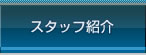食道・胃・十二指腸胸部食道癌 術後の経過と起こり得る合併症
術後の経過
手術終了~翌日
集中治療室(ICU)に入室します。翌日に目を覚まし、人工呼吸器から離脱します。口腔ケアや立位リハビリを開始します。鼻のチューブは帰棟時に抜去します。
術後2日目以降
一般病棟に戻り、歩行リハビリ開始。約1週間は絶飲食で点滴と経管栄養療法を行います。日中は坐位で過ごし、離床を進めていきます。
術後7日目以降
各ドレーン類は適時抜去し、栄養チューブだけとなり、歩行も自由にできるようになります。そのころに嚥下検査を行い、誤嚥ないことを確認し、食事に入ります。
経口摂取開始後
少しずつゆっくり摂取するのが基本です。ゼリー形態、ペースト形態、3分軟食、5分軟食と段階を経て進め、必要に応じて嚥下理学療法士の指導のもと、進めていきます。栄養士もアドバイスをくれます。
順調に行けば術後2-3週間前後で退院します。食事は食べられますが、まだあまり食欲はないことがおおいです。安定して食べられるようになるのは手術から3か月程度経過し、胃の動きが戻ってきたあとになります。それまでは、まだ胃の動きが乏しく、食事が胃の中に長い時間停滞し、ある程度食事を摂取すると胃や喉が詰まったような感じ、重苦しい感じがします。数時間待つと腸の方へ流れていくので、楽になってきてまた食べられるようになるといった状況です。
自宅でも腹部栄養チューブの経腸栄養を継続し、体重減少を予防します。外来栄養指導を受けて、易消化で食べやすい食事をゆっくり摂取して、回復を待ちます。食事の安定を確認して栄養チューブは2-3か月で抜去します。
起こりうる合併症
()内は近畿大学の鏡視下手術での合併症率
反回神経麻痺 ~声が枯れる~
反回神経リンパ節は転移を起こしやすい部位で、細い神経を守ってリンパ節を郭清します。手術や腫瘍の影響で神経麻痺が起こると、声がかすれ(嗄声)、誤嚥にも注意がいります。3か月ほどで治るのですが、残ることもあります。まれですが両側麻痺が起こり、呼吸が苦しくなるときは、気管切開のちリハビリを要します。 (片側麻痺 約9% 両側0.3%)
喀痰排出困難 ~痰がうまくだせない~
食道癌の方は喫煙者が多く、気道周りのリンパ節郭清を行いますので、術後は痰が増えて排痰しづらいこともまれにあります(5%)。
術後肺炎
低侵襲手術では重篤な肺炎は少なくなり、軽度で済みます。誤嚥性肺炎が多いです。ただし肺気腫の既往、高齢者、放射線治療後などは術後早期に肺炎が起こると重症化しやすく危険です。(肺炎 8% 再挿管0.5%)
気腫(気胸、肺瘻、気管瘻)
手術では肺をよけて、気管に接する食道癌を除去します。ときに肺のひどい癒着を外してから癌手術をはじめます。術後に肺や気管から空気漏れると、その空気が頸部や胸まわり、皮下にはいりこんで、ふかふかとした腫れ(気腫)が出現したり、肺が縮んだりすることがあります(気胸)。(気腫 7%)
縫合不全、腸管壊死
食道の代わりに胃を頸部まで持ち上げます。遠い頸部での吻合は血流が弱く緊張が掛かる難しい再建です。縫合不全が起こると発熱、頸部発赤、膿、気腫を認めます。治療には頸部創の開放、鼻から管を通し胃内を減圧する処置、絶食が必要になります。壊死例は再手術を要します。 (縫合不全 4% うち壊死 2%)
リンパ漏
広範囲のリンパ節郭清を行うのではじめは浸出液が多く、徐々に少なくなっていきます。なかなかおさまらない時をリンパ漏と言い、絶食や長期ドレーン留置の必要があり、ときに手術やリンパ管造影が必要になります。(リンパ漏 6%)
嚥下障害 ~飲み込みにくい、熱がでる~
喉に近い癌、放射線治療歴、高齢者、脳梗塞などがリスクで、嚥下力が低下してスムーズに飲み込めない。熱が出る、痰が増えるなどの症状が出ます。嚥下リハビリで改善を目指します。誤嚥性肺炎に注意です。 (誤嚥 5%)
吻合部狭窄
退院後の術後2~3か月目あたりから喉の通りが悪くなり、食べたものがつかえるようになります。吻合部が治癒するにつれて縮んでしまうと起こります。内視鏡で吻合部をバルーンで広げて治します。 (吻合部狭窄 4%)
早期ダンピング症候群 ~食後しんどい~
食事をとると胃の中に食べ物が入って、胃が張ってきます。ホルモンが分泌され、胃に血液が集まり、倦怠感を感じて、しばらくジーっとせざるを得ない感じになります。食べ過ぎには気をつけます。
後期ダンピング症候群 ~ボーっとする、冷や汗がでる~
術後3ケ月を経過すると空腹感もうまれ、食事量が増えてきます。胃の中の食物がすみやかに小腸へ流れてようになるためです。ただその場合、食後早々に栄養吸収が始まって血糖値が上がるので、反応して体が血糖を下げるのですが、それが過度になり低血糖症状(動悸、冷汗、震え、ぼんやりする、気を失う)が出ることがあります。食後2時間あたりで出ます。対策として食後2時間頃にアメ、ジュースなど糖質を取ることを癖づけておくと回避できます。
その他
疼痛、後出血、不整脈、幻覚、不隠、膿胸、腹腔内膿瘍、膵液漏、創感染、血栓症、点滴の感染など
合併症頻度、危険因子、治療関連死
日本消化器外科学会が主導する日本のデータベース(NCD)2014年の全国手術集計からは、合併症は41.9%に認め、創感染は14.8%、縫合不全は13.3%、肺炎は15.4%、腎不全が2.4%、敗血症1.8%に発症し、人工呼吸器を要した例は8.4%、再手術を要した例が8.8%、治療関連死は3.4%に認めたと報告されています。また心疾患、肺疾患、肝硬変、透析歴、高度糖尿病、放射線治療既往、長期ステロイド治療歴、高齢者は合併症発生率が高く、重症化、治療関連死の可能性が高くなります。(Takeuchi er al. Annals of Surgery 2014)
近畿大学では先に示しましたとおり、上記報告例よりはかなり合併症発生率の軽減ができています。2018年以降、2025年8月現在治療関連死は当院では認めていません。